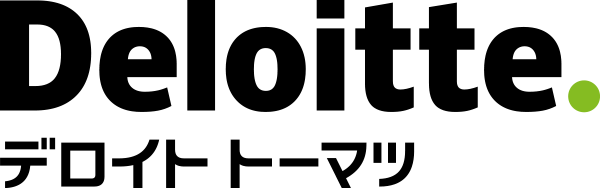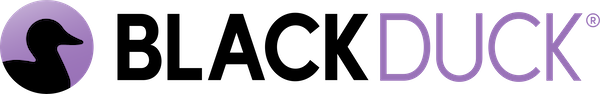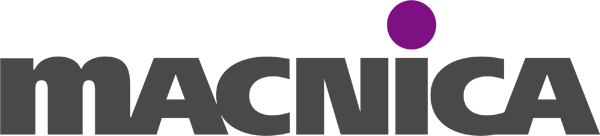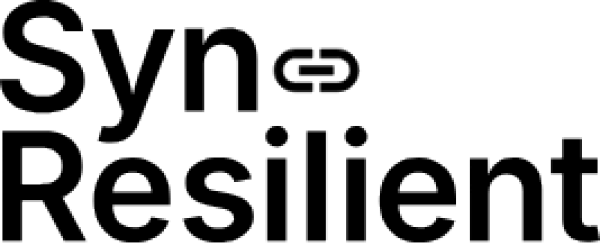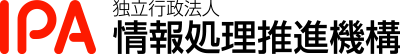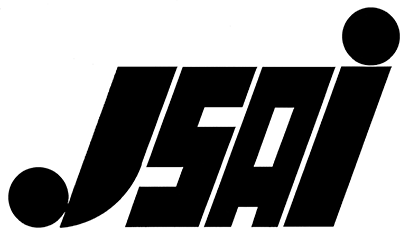“見逃したセッションがあった”
というご要望にお応えし、
期間限定オンデマンド配信を実施しています。
タイムテーブル 9月3日(水)

- 横浜国立大学 先端科学高等研究院
上席特別教授/ - 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
フェロー - 松本 勉
セッション概要
K1 基調講演
信用できるサイバーフィジカルセキュリティ技術の課題と展望
フィジカル世界とサイバー世界をつなぐIoTに係るセキュリティにおける技術を中心とする諸テーマについて展望する。特に、経済安全保障重要技術育成プログラム(K Program)や戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)などにおいて講演者が関与している研究開発から、不正機能検証、人工物メトリクスによる個体管理、耐タンパー技術の体系化、高速秘密計算、高機能暗号、耐量子計算機暗号、AIセキュリティ、AIセーフティ、高機能暗号など関連トピックについても紹介する。
講師

- 松本 勉
- 横浜国立大学 先端科学高等研究院
上席特別教授/ - 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
フェロー
1986年3月、東京大学大学院工学系研究科博士課程修了、工学博士。同年より2024年3月まで横浜国立大学勤務(講師・助教授・教授)。2024年4月より、同大学 先端科学高等研究院 上席特別教授および国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)・フェローに就任、現在に至る。2018年11月から2025年3月まで、産総研・サイバーフィジカルセキュリティ研究センター長を併任した。1981年より理論から社会実装に至る幅広いセキュリティ技術の研究教育と産学官連携に継続して力を注いでいる。
- ナビゲーター
- 国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)
- サイバーセキュリティ研究所 研究所長
- サイバーセキュリティネクサス ネクサス長
- 井上 大介氏

- 一般社団法人JASPAR/本田技研工業株式会社
- 情報セキュリティ推進WG/セキュリティリスクマネジメント部
- 副主査/部長・エグゼクティブチーフエンジニア
- 根本 浩臣 氏
セッション概要
A1-1 招待講演
JASPARの取り組みと自動車セキュリティ
JASPARは、カーエレクトロニクス技術の標準化活動によって、自動車産業全体の開発の生産性向上と技術発展の促進に貢献していきたいと考えている。そのため、JASPAR会員の持つ技術力を活かし、自動車産業を先導する団体を目指している。
自動車セキュリティにおいては、IT領域同様、遠隔からのネットワーク接続に対する脆弱性が脅威となるのに加え、自動車が野外で使われる特性上、近距離通信の脆弱性を悪用した脅威も想定する必要がある。また、対策技術の検討・標準化には、その自動車特有の脅威に加え、実装上の制約を考慮する必要がある。
本講演では、JASPARの活動やその成果物である文書についてご紹介する。
講師

- 根本 浩臣 氏
- 一般社団法人JASPAR/本田技研工業株式会社
- 情報セキュリティ推進WG/セキュリティリスクマネジメント部
- 副主査/部長・エグゼクティブチーフエンジニア
1990年本田技研工業入社、4輪パワートレイン、NV、車両制御関連の電装システム開発を経て、2016年より車両サイバーセキュリティ業務に従事、現在に至る。自動車業界標準化活動として、2016年一般社団法人JASPAR_情報セキュリティWGに参画し副主査を務める、また、2023年から一般社団法人Japan Automotive ISAC理事に就任し、現在に至る

- 横浜国立大学
- 大学院環境情報研究院および先端科学高等研究院
- 教授
- 吉岡 克成
セッション概要
B1-1 招待講演
DarkWRT: IoT機器向け不正機能埋込テストベッドと疑似攻防サイクルによる対策技術の深化
複雑化するサプライチェーンの中で、情報漏洩や侵入の原因となる不正機能が悪意をもって混入される事例が報告されている。しかし、これら不正機能の実態は明らかでなく、対策技術の研究開発の障壁となっている。我々は、不正機能検知技術の評価を目的とし、ルータ等の組み込み機器向けオープンソースLinuxディストリビューションであるOpenWRTに不正機能を付加したテストベッド「DarkWRT」を開発した。現実世界の不正機能の事例を反映し組み込み、セキュリティ専門家の知見とLLMを活用しながら疑似攻防サイクルを繰り返し、潜在的脅威の先回り的把握を目指す取り組みについても報告する。
講師

- 吉岡 克成
- 横浜国立大学
- 大学院環境情報研究院および先端科学高等研究院
- 教授
2005年よりNICTにてインシデント対策センターNICTERの研究開発に従事。2008年より横浜国立大学にてサイバーセキュリティ研究開発を開始。総務省「電波の有効利用のための IoT マルウェア無害化/無機能化技術等に関する研究開発」、NEDO「KPRO・先進的サイバー防御機能・分析能力の強化」他、国プロに多数参画。サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議 構成員、IPAセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR) 技術審議委員会委員長等。博士(工学)。

- PwCコンサルティング合同会社
- Industry Transformation - Smart Mobility
- シニアマネージャー
- 亀井 啓 氏
セッション概要
A1-2 特別講演
SDV時代の自動車サイバーセキュリティ
SDVの普及によって、車両に搭載されるソフトウェアの総量やアップデート頻度が増加し、車両開発や品質保証の在り方そのものも大きく変化しつつある。また、ソフトウェア価値が高まることで、車両がサイバー攻撃の標的となるリスクの増大も予見される。本セミナーでは、SDVの概観と、SDVがもたらすセキュリティへの影響を整理し、セキュリティ監視、組織ガバナンス、AI・データ活用などの技術利用に伴うデジタル法規対応など、今後不可欠となるアジェンダを紹介する。
講師

- 亀井 啓 氏
- PwCコンサルティング合同会社
- Industry Transformation - Smart Mobility
- シニアマネージャー
グローバル製造業を経てPwCコンサルティング合同会社に入社。
自動車業界を中心とした製造業向けの製品サイバーセキュリティに関する支援プロジェクトに従事し、PSIRT・セキュアプロセス構築、脅威分析、欧州を中心とした各種デジタル法規対応、国際標準への準拠活動、各種ソリューションの導入などさまざまなテーマを担当。

- 株式会社ユビキタスAI
- 取締役副社長 COO
- 古江 勝利 氏
セッション概要
B1-2 特別講演
「Security by Design」が必然となってきた理由と背景をセキュリティ検証事業者の視点で分析する
CRAやJC-STAR等の登場によって、IoT機器のセキュリティ対策への関心が高まっているのは間違いない。しかし、現状は脆弱性レポート等のアラートに対してソフトウェアアップデート形式による対策を実施するのみで、IoT機器自体が市場リリース時に十分堅牢であるという設計思想では無いと感じる。そのため攻撃者による「乗っ取り」や「なりすまし」だけでなく「異常動作」や「システム停止」を引き起こす不正機能を埋め込まれてしまうリスクがあることが、様々な機器を検証すると見えてくる。ここではSecurity by Designの必然性を、IoT機器の事例を基に説明し、実現するための要素技術について解説する。
講師

- 古江 勝利 氏
- 株式会社ユビキタスAI
- 取締役副社長 COO
米国半導体メーカーでプロダクト・マーケティング・スペシャリストとして、様々なプロダクトの日本市場におけるビジネス開拓に従事。2000年代終盤からArmプロセッサベースのマイコンビジネスで、日本の組込みパートナー協業モデルによるソリューションセールスの成功を推進。2016年より北欧の組込みソフトウェア開発ツールメーカーの日本市場向けブランドマーケティングとプロダクトプロモーションに貢献。2021年にユビキタスAIに参加し、近年はツール製品とセキュリティビジネスに注力し事業拡大に従事している。
- ナビゲーター
- PwCコンサルティング合同会社
- トラストコンサルティング
- ディレクター
- 奥山 謙氏
- ナビゲーター
- 株式会社ユビキタスAI
- 企画室
- 担当部長
- 伊藤 准 氏

- 国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)
- サイバーセキュリティ研究所 サイバーセキュリティ研究室
- 森 好樹 氏
セッション概要
L1 基調講演
NICTER観測:マルウェアに感染したIoT機器の実態とその対策~2025~
本セッションでは、NICTERで観測されたマルウェア感染IoT機器のうち、2025年に確認されたブロードバンドルータ、および2022~2025年に継続的に観測されたデジタルビデオレコーダーを対象に、感染台数、感染経路などを紹介する。加えて、攻撃者インフラの詳細調査によって得られた分析結果や、実際に講じた封じ込め対策とその効果についても解説する。
講師

- 森 好樹 氏
- 国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)
- サイバーセキュリティ研究所 サイバーセキュリティ研究室
通信ネットワーク事業者にてNOC/SOC業務およびネットワーク構築業務を経験後、2017年度に国立研究開発法人 情報通信研究機構に入所。ダークネット宛のパケットの分析業務に従事。日々、日本国内でマルウェアに感染したIoT機器を調査。Black Hat Europe 2023 Briefingsにてルーター製品に搭載されるDDNS機能の脆弱性について発表。
ICカードに始まる日欧セキュリティ連携の進化
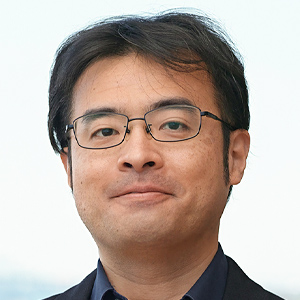
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所/ICシステムセキュリティ協会
- サイバーフィジカルセキュリティ研究センター セキュリティ保証スキーム研究グループ
- 研究グループ長/事務局長
- 吉田 博隆 氏
セッション概要
A2-1 招待講演
ICシステムセキュリティ協会の「知る人ぞ知る」から「知らぬものなき」への挑戦:
ICカードに始まる日欧セキュリティ連携の進化
ICシステムセキュリティ協会(ICSS-RT)は2009年に設立され、ICカード向けを中心としたデバイスならびにアプリケーションシステムに関するセキュリティ技術を協議してきた。2022年には、ICSS-RTは、軽量な組込み機器向けチップ等を検討する分科会を設立させた。また、2025年には、セキュリティ認証に関する欧州の非営利団体EUCC ISACにおいて、ICSS-RT内の部会(ICSS-JC)が準会員としての参加資格を獲得した。現在、ICSS-RTは、IoT機器に搭載するソフトウェアの印加(書き込み)等を検討するユーザーフォーラムの新設置を検討中である。本講演では、ICSS-RTのオープンな取り組みを紹介する。
講師
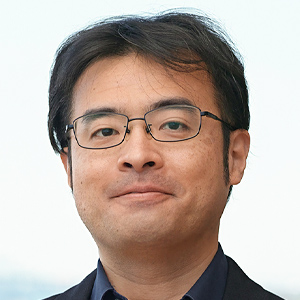
- 吉田 博隆 氏
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所/ICシステムセキュリティ協会
- サイバーフィジカルセキュリティ研究センター セキュリティ保証スキーム研究グループ
- 研究グループ長/事務局長
2013年 KU Leuven Department of Electrical Engineering 博士課程修了。
2001-2015年に日立製作所研究員、2016年より産業技術総合研究所 入所。
現在、産業技術総合研究所 サイバーフィジカルセキュリティ研究センター セキュリティ保証スキーム研究グループ長。2022年4月よりICシステムセキュリティ協会 事務局長。セキュリティ保証スキームとIoT向け暗号技術に関する研究に従事。

- 特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)
- 調査研究部会 OTセキュリティWG サブリーダー/
- フォーティネットジャパン合同会社 OTビジネス開発部 担当部長/
- 名古屋工業大学 産官学金連携機構 ものづくりDX研究所 外部研究員
- 藤原 健太 氏
セッション概要
B2-1 招待講演
DXとセキュリティは表裏一体! JNSAが取り組むOTセキュリティの文化醸成と本質的対策の推進
DXの進展と共にOTセキュリティの考慮は必要不可欠である。その本質は、ITセキュリティで基本要素とされてきた「機密性・完全性・可用性(CIA)」に加え、「安全性(Safety)」の確保にある。JNSA 調査研究部会OTセキュリティWGでは、2024年8月WG発足来、この視点を基に「現場の安心・安全と生産活動の維持」を目的とした対策手法を展開し、38社、76名(2025/6月現在)がOTセキュリティの文化醸成と、実践的な支援に取組んでいる。本講演では、WG発足と活動内容を紹介すると共に、工場をはじめとするOT領域において「何を、どう守るのか」を再定義し、OTセキュリティのあるべき姿を提示する。
講師

- 藤原 健太 氏
- 特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)
- 調査研究部会 OTセキュリティWG サブリーダー/
- フォーティネットジャパン合同会社 OTビジネス開発部 担当部長/
- 名古屋工業大学 産官学金連携機構 ものづくりDX研究所 外部研究員
生まれも育ちもOT畑、安全とサイバーセキュリティを同時に考える人材として、訪問したプラント・工場は80拠点以上に渡る。
これまで現場機器から制御システム、OT領域のデジタル化支援まで幅広く従事し、直近では機能安全(FS)、安全計装システム(SIS)に携わった経験から製造業を始めとするOT領域のリスクの考え方に精通する。これらの経験を活かしてOTセキュリティに関する、業界紙・メディア連載、イベント登壇、各社・各省向け教育に従事し、OTセキュリティの文化醸成に努めている。

- 株式会社セカフィー
- 代表取締役
- 門田 和樹 氏
セッション概要
A2-2 特別講演
ICチップレベルで物理攻撃を対策するセキュリティ技術
IoT機器の普及に伴い、サイドチャネル攻撃やフォールトインジェクション攻撃といった物理攻撃の脅威が顕在化する。本講演では、これらの攻撃に対する半導体ICチップレベルの対策として、半導体回路レベルおよびパッケージ実装レベルで実現可能なハードウェアセキュリティ技術、および、半導体設計における物理攻撃シミュレーションについて解説する。ICチップのセキュリティ物理攻撃対策について、回路・実装・シミュレーション技術の役割と今後の展望について考察する。
講師

- 門田 和樹 氏
- 株式会社セカフィー
- 代表取締役
2024年に神戸大学にて博士(科学技術イノベーション)を取得。在学中にはサイドチャネル攻撃やフォールトインジェクション攻撃に関するシミュレーション技術と、回路・パッケージレベルでの対策技術の研究開発に取り組んだ。2023年、ハードウェアセキュリティ分野における研究成果を基に株式会社セカフィーを共同創業。現在は代表取締役として、サイドチャネル攻撃や故障注入攻撃に対する評価・対策技術の社会実装に取り組んでいる。

- 株式会社日立ソリューションズ
- セキュリティソリューション事業部 企画本部
- OTセキュリティ推進センタ センタ長
シニアセキュリティエバンジェリスト
/早稲田大学グローバルエデュケーションセンター 非常勤講師 - 扇 健一 氏
セッション概要
B2-2 特別講演
未来を見据えた工場DX戦略 〜インフラとセキュリティの両立をめざして~
近年、IoTや生成AIなどの技術の進展や顧客ニーズの多様化を背景に、工場DXの推進が急務となっている。工場DXの実現にはネットワークを含むインフラの整備が欠かせないが、併せて考慮しなければならないのがセキュリティだ。セキュリティを無視したDX推進はサイバー攻撃の標的となるリスクが高まるだけでなく、万が一攻撃を受けた場合、工場システムが停止し企業全体の事業継続に影響を及ぼす可能性がある。本セッションでは、未来を見据えた工場DXの推進にあたり、インフラ整備とセキュリティ強化をどのように両立させるかについて、押さえておきたいポイントや推進ステップを紹介する。
講師

- 扇 健一 氏
- 株式会社日立ソリューションズ
- セキュリティソリューション事業部 企画本部
- OTセキュリティ推進センタ センタ長
シニアセキュリティエバンジェリスト
/早稲田大学グローバルエデュケーションセンター 非常勤講師
早稲田大学 グローバルエデュケーションセンター非常勤講師。20年以上にわたり開発から導入までセキュリティ関連業務に従事し、特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会やVirtual Engineering Communityなどのセキュリティ関連団体において社会貢献活動も行う。
ダイワボウ情報システム(株)PC-Webzineにてセキュリティ記事「CYBER GUARDIAN」連載中のほか、著書に技術評論社「今さら聞けないIT・セキュリティ必須知識 クイズでわかるトラブル事例」がある。
- ナビゲーター
- 横浜国立大学 先端科学高等研究院 上席特別教授/
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 フェロー
- 松本 勉
- ナビゲーター
- 株式会社 日立ソリューションズ
- セキュリティソリューション事業部 セキュリティプロダクト本部
- セキュリティマーケティング推進部 第1グループ
- ユニットリーダ
- 原 紫野美氏

- 株式会社ラック
- 技術統括部 セキュアソリューションユニット
- ユニット長
- 木村 芳教 氏
セッション概要
AB3 ソリューション講演
船舶のIoT化に伴うサイバーセキュリティの重要性
船舶のデジタル化が進む中、IoT技術の導入は効率化をもたらす一方で、サイバーリスクの脅威が高まっている。
本セッションでは、船舶を狙うサイバー攻撃の実態を解説するとともに、日本初の実運航船を用いたサイバー防御演習の内容や、具体的なペネトレーションテストの手法。現在取り組んでいる事例を紹介する。
講師

- 木村 芳教 氏
- 株式会社ラック
- 技術統括部 セキュアソリューションユニット
- ユニット長
攻撃者目線であらゆる環境へ侵入するペネトレーションテストや、セキュリティの基礎となるWeb、プラットフォームをはじめとした診断部門。ならびにEC開発などのソリューション開発を含めた事業の責任者
ロータス、IBMを経て、2015年に当時子会社のネットエージェントへ入社
2020年 会社統合によりラックへ転席 ペネトレーションテストを主とするデジタルペンテスト部を設立
2024年 同部の上層にあたるセキュアソリューションユニットを設立
現在に至る

- 経済産業省
- 商務情報政策局サイバーセキュリティ課
- 課長
- 武尾 伸隆 氏
セッション概要
A4-1 招待講演
産業分野におけるサイバーセキュリティ政策とJC-STAR制度について
IoT製品の活用が進む中、その脆弱性を狙ったサイバー攻撃の脅威が高まっている。諸外国では消費者用IoT製品のセキュリティ対策を義務化するなど対策強化の動きが広がっている。
本講演では、経済産業省が推進している産業分野におけるサイバーセキュリティ政策の全体像及び2025年3月に開始したIoT製品に対するセキュリラベリング制度であるJC-STARの概要、普及促進施策と今後の展望等について紹介する。
講師

- 武尾 伸隆 氏
- 経済産業省
- 商務情報政策局サイバーセキュリティ課
- 課長
神奈川県出身。平成14年経済産業省入省。防衛・航空機・宇宙産業、産学官連携支援などに従事後、新エネルギー・産業総合開発機構(NEDO)欧州事務所長や情報技術利用促進課長、電池産業室長を経て、令和5年7月より、現職。DX経済実現に不可欠なサイバー脅威への対応(サプライチェーン全体でのセキュリティ対策の促進など)を担当。

- 日本経済新聞社
- 編集局
- 記者
- 寺岡 篤志 氏
セッション概要
B4-1 招待講演
米国のサイバー安保動向と日本への示唆
世界随一のサイバー大国、米国も新政権の発足を受け、日本と同様サイバー安保政策の変革の過渡期にあります。米国でサイバー軍が発足したのは2009年、その後の過程で起きてきた数々の課題は今後日本が直面しうる問題でもあります。米国の現在地から日本が学ぶ教訓、受ける影響は何か。半年間の米国での研究をもとにお話しします。
講師

- 寺岡 篤志 氏
- 日本経済新聞社
- 編集局
- 記者
2008年、日本経済新聞社入社。14年にマウントゴックス社のビットコイン消失事件の取材にあたったことをきっかけにセキュリティ関連の取材を開始。22年からセキュリティの専任記者。同年度に九州大学サイバーセキュリティセンターの教育訓練プログラム修了。24年、英国政府によるサイバーセキュリティフェローシッププログラムに一期生として参加。25年、フルブライト奨学金を受けてメリーランド大学カレッジパーク校客員研究員として渡米し、米国のサイバー安保政策の研究のため120人以上の専門家の取材に携わる。

- NECセキュリティ株式会社
- IoT/OTセキュリティユニット
- ディレクタ(ユニット長)
- 桑田 雅彦 氏
セッション概要
A4-2 特別講演
~ 法規制/制度運用が開始!対応が急務に ~ IoT/OTデバイスに求められるセキュリティ対策の最新動向紹介
自動車やドローンなどのモビリティ、ロボット、FA機器、船舶機器、建機、農機、医療機器、監視カメラなど、様々なIoT/OTデバイスの導入/活用により、モノにかかわるDX(デジタル変革)が急速に進展しつつある中、IoT/OTデバイスにかかわるセキュリティリスクが増大し、その対策は、経済安全保障推進法やEUサイバーレジリエンス法、JC-STARなど法規制/制度対応としても急務である。
法規制/制度の最新動向とともに、IoT/OTデバイスに求められるセキュリティ対策とはどのようなものか、その課題は何かを解説し、IoT/OTデバイスの特性/制約に適用可能なセキュリティ対策製品の最新情報や事例を紹介する。
講師

- 桑田 雅彦 氏
- NECセキュリティ株式会社
- IoT/OTセキュリティユニット
- ディレクタ(ユニット長)
30年以上にわたり、サイバーセキュリティ関連業務に従事。
当初の専門領域は、ID/アクセス管理、認証/認可(アクセス制御)のソフトウェア技術。
その後、サイバーセキュリティ全体へ守備範囲を拡張。
最近10年ほどは、IoT/OTシステム向けセキュリティ対策の企画/開発/提案を推進。
JNSA/OTセキュリティWG/SWG2(工場セキュリティWGから移行)のリーダを務め、
工場セキュリティガイドラインのエディタ及び主要執筆者。
経済産業省 産業サイバーセキュリティ研究会 WG1 工場SWG 委員。

- 株式会社マクニカ
- ネットワークスカンパニー DXソリューション事業部 第2技術部 第1課
- 野田 紘司 氏
セッション概要
B4-2 特別講演
生成AI時代の開発とセキュリティの新バランス 〜レビューが追いつかない時代の“先回り型”対策とは〜
生成AIの活用が進むことで、開発の生産性は飛躍的に向上しています。一方で、成果物の量が増加することでコードレビューやセキュリティチェックの負荷は増し、「リリース直前に脆弱性が発覚する」といった事態も起こりやすくなっています。
こうした背景から、従来の後工程での対応ではなく、開発初期段階からセキュリティを組み込む“先回り型”のアプローチ、すなわち「シフトレフト」が今まで以上に重要になっています。
本セッションでは、SASTやSCAなどのアプリケーションセキュリティ対策をどのように開発プロセスへ組み込み、開発現場のスピードと品質を両立させていくかをご紹介します。セキュリティの内製化や自動化を支援するための実践的な選択肢と、その導入効果についてお伝えします。
講師

- 野田 紘司 氏
- 株式会社マクニカ
- ネットワークスカンパニー DXソリューション事業部 第2技術部 第1課
組み込み系システムの開発に従事した経験を活かし、2021年よりマクニカにてGitHubやBlack Duckなど、開発者向け製品の提案・技術サポートを担当。
SCMやCI/CD環境との統合、DevSecOpsの実現に向けた技術支援を数多く手がけている。
企業の中核となる開発業務を、よりセキュアかつ効率的に進めるための手法を日々追求している。
- ナビゲーター
- 国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)
- サイバーセキュリティ研究所 研究所長
- サイバーセキュリティネクサス ネクサス長
- 井上 大介氏
- ナビゲーター
- 株式会社マクニカ
- ネットワークスカンパニー DXソリューション事業部 第2営業部 第1課
- 山岸 朋弥氏

- パネリスト
- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
- セキュリティセンター
- フェロー/技術評価部 部長
- 神田 雅透 氏

- パネリスト
- NECプラットフォームズ株式会社
- セキュリティ・IT統括部
- 統括部長
- 澤田 利幸 氏

- パネリスト
- 横浜市
- デジタル統括本部
- CIO補佐監
- 福田 次郎 氏

- パネリスト
- 株式会社ECSEC Laboratory
- 評価センター
- 取締役
- 川岸 敏之 氏

- パネリスト
- PwCコンサルティング合同会社
- トラストコンサルティング
- ディレクター
- 奥山 謙 氏

- モデレーター
- 横浜国立大学 先端科学高等研究院
上席特別教授/ - 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
フェロー - 松本 勉
セッション概要
P1 パネルディスカッション
JC-STARの挑戦 ~制度設計・運営、IoT機器製造販売・調達、適合性検証/評価、ラベル発行/認証の観点からセキュリティラベリング制度を展望~
我が国で2025年から運用が開始された「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR: Labeling Scheme based on Japan Cyber-Security Technical Assessment Requirements)」の現状と未来につき、この制度のステークホルダーである制度設計者/運用者、IoT機器ベンダー/調達者・購入者、ラベル発行機関/認証機関、そして検証事業者/評価機関のそれぞれの視点から立体的に語り合います。司会進行はIoTセキュリティ研究者が担当します。
講師

- 神田 雅透 氏
- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
- セキュリティセンター
- フェロー/技術評価部 部長
1993年東工大大学院修士課程修了、NTT入社。情報セキュリティ・暗号研究に従事し、「Camellia」暗号開発を担当。2020年IPA入構。暗号政策・CRYPTREC、セキュリティ製品認証(CC、JCMVP、JC-STAR)を担当。2024年技術評価部部長、2025年7月IPAセキュリティセンターフェロー。2023年より個人情報保護委員会専門委員兼務。博士(工学)。平成26年度文部科学大臣表彰。

- 澤田 利幸 氏
- NECプラットフォームズ株式会社
- セキュリティ・IT統括部
- 統括部長
社会インフラシステムの開発・設計を通じて、制御システムやIoT機器におけるセキュリティの重要性を痛感。セキュリティ専門会社で業務経験を積み、現在はIoT機器等のハードウェア生産会社で製品や生産工場のセキュリティ強化に取り組んでいる。
世の中の全てのIoT機器を、誰もがセキュアで安心・安全に使える未来を目指し、”つくる側の立場”から様々な社会貢献活動に参画中。

- 福田 次郎 氏
- 横浜市
- デジタル統括本部
- CIO補佐監
1989年三菱総合研究所に入所、都市インフラやICT・インターネットビジネスの調査・企画に従事。2015年より、横浜市最高情報統括責任者(CIO)補佐監に就任。CISO補佐監を兼任。DX戦略、スマートシティ、EBPMなどを推進。庁内システムの企画設計やAI・IoT導入にも積極的に取り組む。デザイン思考・システム思考を活かし、自治体課題の可視化と解決策の提案を行っている。IPA JC-STAR技術審議委員会委員。

- 川岸 敏之 氏
- 株式会社ECSEC Laboratory
- 評価センター
- 取締役
ICカード及び周辺端末の開発・設計に従事し、EMVCo認証やCC認証などの製品セキュリティ認証取得に携わる。2017年よりECSEC Labにて、試験所(ISO/IEC 17025)のマネジメント業務を主に担当。CC認証及び暗号モジュール認証に加え、PSA Certified/SESIPの試験所資格取得を推進。現在は、JC-STAR評価機関としての認定取得に向けた活動を中心に担当。

- 奥山 謙 氏
- PwCコンサルティング合同会社
- トラストコンサルティング
- ディレクター
製品開発におけるセキュリティ対策の分野において長年の豊富な経験を持ち、製品およびソフトウェア開発におけるセキュア開発ガイドラインの策定、セキュア開発活動の監査、開発者支援および教育、製品リリース後の脆弱性マネジメントなどの経験を有する。
内閣府主導の「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」などの業務に従事し、車両セキュリティ評価などの活動をリード。組み込み製品やソフトウェアサービスなどのソフトウェア開発の経験を通じて、実践的なセキュリティ対策提案などで貢献。

- 松本 勉
- 横浜国立大学 先端科学高等研究院
上席特別教授/ - 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
フェロー
1986年3月、東京大学大学院工学系研究科博士課程修了、工学博士。同年より2024年3月まで横浜国立大学勤務(講師・助教授・教授)。2024年4月より、同大学 先端科学高等研究院 上席特別教授および国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)・フェローに就任、現在に至る。2018年11月から2025年3月まで、産総研・サイバーフィジカルセキュリティ研究センター長を併任した。1981年より理論から社会実装に至る幅広いセキュリティ技術の研究教育と産学官連携に継続して力を注いでいる。
ささやかではございますが、立食形式にてお食事もご提供いたします。
オンライン展示をご希望の方
-
本フォーラム内でソリューションの展示をいただけるご協賛企業・団体を募集しております。
ご希望・ご検討の方は下記の事務局までお問い合わせください。
協賛プログラムに関する詳細資料やお申込書等をご案内いたします。「IoTセキュリティフォーラム」事務局
E-mail:iotsecurity-forum@impress.co.jp
受付時間 10:00〜18:00(土・日・祝を除く)