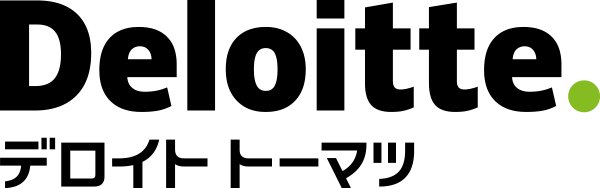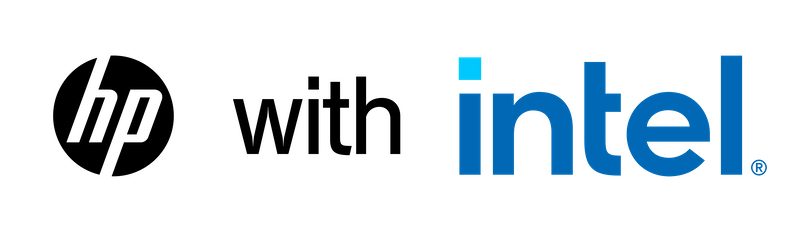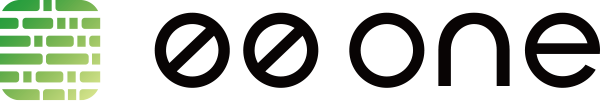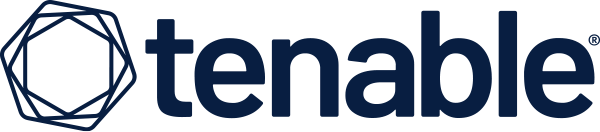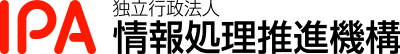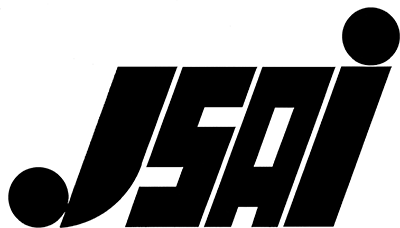たくさんのお申込をいただきありがとうございました。
“見逃したセッションがあった”
というご要望にお応えし、
期間限定オンデマンド配信を実施しています。
タイムテーブル 9月4日(水)

- 横浜国立大学
- 大学院環境情報研究院および先端科学高等研究院
- 教授
- 吉岡 克成
セッション概要
K2 基調講演
増大する脅威に対抗する次世代のサイバーセキュリティ情報収集分析技術 ~技術的・非技術的挑戦~
サイバー攻撃の頻度、規模が増大し、その被害が顕著になっている。従来からの対処療法的な対策だけではなく、各組織・個人が自己の状況を正しく認識し、脆弱性や設定不備といった対策を継続的に行うと共に、攻撃動向観測や脅威インテリジェンス等の活用により攻撃の兆候や準備段階を認知するプロアクティブな対策がこれまで以上に重要になっている。本講演では、横浜国大での15年に及ぶ攻撃観測・分析研究の知見に基づき、増大する脅威に対抗するための新たな情報収集分析技術の必要性と構想について説明すると共に、その技術的・非技術的な挑戦と限界について考察する。
講師

- 吉岡 克成
- 横浜国立大学
- 大学院環境情報研究院および先端科学高等研究院
- 教授
2005年より(独)情報通信研究機構にてインシデント対策センターNICTERの研究開発に従事。2008年より横浜国立大学にてサイバーセキュリティ研究開発を開始。2009年文部科学大臣表彰。総務省「国際連携によるサイバー攻撃の予知即応技術の研究開発」「電波の有効利用のための IoT マルウェア無害化/無機能化技術等に関する研究開発」他、プロジェクトに多数参画。博士(工学)。
- ナビゲーター
- 国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)
サイバーセキュリティ研究所 研究所長 - サイバーセキュリティネクサス ネクサス長
- 井上 大介氏
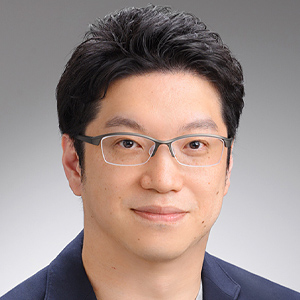
- GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社
- 常務取締役CTO of Development
- 菅野 哲 氏
セッション概要
A5-1 招待講演
耐量子計算機暗号(PQC)とIoT機器の最新動向
現在、耐量子計算機暗号(PQC)は、「暗号の2030年問題」の1つとして大きな注目を集めている。PQCの利用に向けてNISTやIETFといった国際的な組織で検討が行われ、実際のインターネットでの利用が進行中である。例えば、ブラウザでは現行暗号とPQCのハイブリッドモードでの利用がある。
本セッションでは、PQCに関する情報を整理した上で標準化動向を含む技術動向を踏まえてIoT機器への影響や暗号移行に関する現状について報告する。
講師
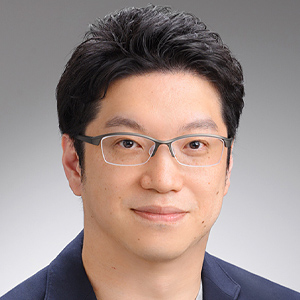
- 菅野 哲 氏
- GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社
- 常務取締役CTO of Development
電気通信大学 修了。NTTソフトウェア株式会社(現 NTTテクノクロス株式会社)を経て、株式会社レピダム(現 GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社)が現職。
IETFにおいてTLSやIPsecプロトコルに関するRFCを多数発行している。近年では、秘密計算に基づくデータ利活用や6G時代に必要なる低遅延暗号、暗号の「2030年問題」で注目されるPQCなどの技術領域で活動中。

- 国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)
- サイバーセキュリティ研究所 サイバーセキュリティ研究室
- 研究技術員
- 森 好樹 氏
セッション概要
B5-1 招待講演
NICTER観測:マルウェアに感染したIoT機器の実態とその対策
本セッションでは、NICTERで観測されたマルウェアに感染したIoT機器について紹介する。感染台数、攻撃を受けた機器の詳細、感染経路に加え、SIMカード搭載可能な通信モジュールを持つIoT機器のプロダクトインシデントについても解説する。さらに、どのような対策を講じるべきだったのか、実際にどのような対応をしたのかも含めて紹介する。
講師

- 森 好樹 氏
- 国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)
- サイバーセキュリティ研究所 サイバーセキュリティ研究室
- 研究技術員
通信ネットワーク事業者にてNOC/SOC業務およびネットワーク構築業務を経験後、2017年に国立研究開発法人 情報通信研究機構に入所。ダークネット宛のパケットの分析業務に従事。日々、日本国内でマルウェアに感染したIoT機器を調査。Black Hat Europe 2023 Briefingsにてルーター製品に搭載されるDDNS機能の脆弱性について発表。

- DigiCert Inc.
- Research and Development
- Vice President
- Avesta Hojjiati
(アベスタ ホジャッティ) 氏
セッション概要
A5-2 特別講演
未来を守る: 迫る量子コンピュータの脅威にメーカーとしてどう取り組むのか ~Protecting the Future: How Manufacturers Can Harness Quantum Computing~ ※英語→日本語 同時通訳あり
企業は量子コンピュータがもたらす脅威に対処するために、想定よりも早く技術移行の計画に取り組み始める必要がある。本セッションでは、量子コンピュータ対策のスケジュール、その潜在的な影響、いま組織が行うべきこと、そしてIoTメーカー向けに移行プラン策定の段取りについて説明する。
原文:Organizations need to start planning for the technology migration to address the threats posed by quantum computing sooner than anticipated. In this session, we will discuss the timelines for quantum computing, its potential impacts, current organizational preparations, and how IoT manufacturers can begin defining an effective migration strategy.
講師

- Avesta Hojjiati(アベスタ ホジャッティ) 氏
- DigiCert Inc.
- Research and Development
- Vice President
米国DigiCertの研究開発担当VPであり、組み込み/IoTデバイスセキュリティやポスト量子暗号(PQC)ソリューションなどのサイバーセキュリティ製品群の開発を主導するほか、M&A戦略と連動した広範な製品ロードマップ開発にも関与している。国際暗号研究協会(IACR)のメンバーで、アメリカ国立標準技術研究所(NIST)のPQCアルゴリズムのレビューなどを行うPQC移行プロジェクトのサポートメンバーとしても活動している。
原文:Avesta Hojjati is the VP of Engineering at DigiCert, who leads the advanced development of a suite of cybersecurity products, including embedded/IoT device security and post-quantum cryptography (PQC) solutions, in addition to influencing the broader product roadmap in conjunction with the M&A strategy.
Avesta is a member of the International Association for Cryptologic Research (IACR) and a supporting member of the PQC Transition Project, which includes a review of the PQC algorithm at the National Institute of Standards and Technology (NIST).
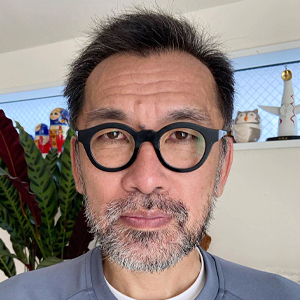
- 株式会社レインフォレスト
- 代表取締役
- 岡田 晃市郎 氏
- ※本講演は株式会社クルウィットによる提供です。
セッション概要
B5-2 特別講演
Censys, ASM, kr:ns を利用したデータ解析
Censys, ASM, kr:ns(クロノス)を利用して、インターネット上から見えるIT資産情報の特定や脆弱性収集方法を紹介する。
そして、これらのツールにより得られた結果から、攻撃の傾向や特徴の具体的な手法と事例を説明する。
講師
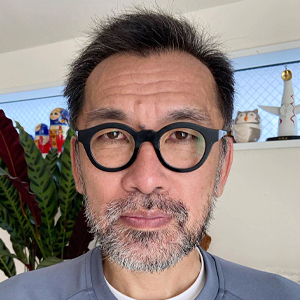
- 岡田 晃市郎 氏
- 株式会社レインフォレスト
- 代表取締役
セキュリティ企業にて、マルウェア解析や観測データを活用し、不正送金対策ソリューションの開発に従事。
2018年にレインフォレストを立ち上げ、サイバーセキュリティに関連する研究開発、IPレピュテーションサービスkr:nsやCensysを利用したASMツールの開発とリリース行う。
また、横浜国立大学において、IoTマルウェアの研究に従事。
- ナビゲーター
- 横浜国立大学 先端科学高等研究院 上席特別教授/
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 フェロー
- 松本 勉
- ナビゲーター
- 株式会社クルウィット
- 代表取締役
- 国峯 泰裕氏
ホームネットワークへのサイバー攻撃の過去・現在・未来

- 横浜国立大学
- 大学院環境情報研究院および先端科学高等研究院
- 教授
- 吉岡 克成
セッション概要
A6-1 招待講演
あなたの家が狙われる!?
ホームネットワークへのサイバー攻撃の過去・現在・未来
家庭のIoT機器がサイバー攻撃の対象となることが様々な研究や報道により取り上げられるようになって久しいが、攻撃の実態や被害について具体的に示される例は限られている。そのため、対策が必要な事項が見逃されたり、逆に、非現実的な脅威を想定した不必要な対策が導出される恐れがある。本講演では、これまでの攻撃事例や研究成果を概観、整理し、攻撃の実態や現実的な脅威を抽出し、その時間的変遷を説明する。また、今後発生し得る脅威について考察する。
講師

- 吉岡 克成
- 横浜国立大学
- 大学院環境情報研究院および先端科学高等研究院
- 教授
2005年より(独)情報通信研究機構にてインシデント対策センターNICTERの研究開発に従事。2008年より横浜国立大学にてサイバーセキュリティ研究開発を開始。2009年文部科学大臣表彰。総務省「国際連携によるサイバー攻撃の予知即応技術の研究開発」「電波の有効利用のための IoT マルウェア無害化/無機能化技術等に関する研究開発」他、プロジェクトに多数参画。博士(工学)。

- オートリブ株式会社
- 品質本部
- テクニカルアドバイザー
- 益 啓純 氏
セッション概要
B6-1 招待講演
オートリブにおける工場セキュリティへの取り組みの紹介
現在、自動車業界に求められているサイバーセキュリティへの対応が求められている。その中で自動車部品メーカーとして、どのように工場セキュリティへ取り組んでいるかについて、これまでの活動にいたるまでの経緯と、弊社筑波工場で実施したリスク評価について紹介する。
講師

- 益 啓純 氏
- オートリブ株式会社
- 品質本部
- テクニカルアドバイザー
マツダ株式会社にて、主にブレーキ系制御システム開発に従事
ジェイテクト株式会社 EPS制御システムの開発に従事
MBD、機能安全、A-SPICEの仕組みの立ち上げ
工場のDX化の推進
オートリブ株式会社 機能安全、A-SPICEの仕組みの立ち上げ
工場セキュリティの推進
自動車技術会 機能安全分科会委員
RRI 産業セキュリティワーキング メンバー

- 株式会社ユビキタスAI(Ubiquitous AI Corporation)
- 取締役
- エンベデッド第3事業部長
- 古江 勝利 氏
セッション概要
A6-2 特別講演
スマートホーム普及の鍵となるHEMS機器のセキュリティ対策と運用のポイント
住宅のスマート化への需要の高まりとそれに対応するIoT機器の増加によってスマートホーム化が急速に進んでいる。スマートホームによってもたらされるメリットは多岐にわたり、住宅そのものの管理、防犯および省エネといった面から、高齢化社会における健康管理や見守りまで、テクノロジーによる「見える化」が様々な課題を解決してくれると評価されている。一方で、スマート化によるセキュリティリスクへの認識不足が大きな懸念となっている。本セッションではスマートホームの重要デバイスであるHEMS機器による住宅設備のセキュリティリスクと対策について検証し考察する。
講師

- 古江 勝利 氏
- 株式会社ユビキタスAI(Ubiquitous AI Corporation)
- 取締役
- エンベデッド第3事業部長
1992年に日本モトローラ半導体セクター入社。後に分社化されたフリースケールセミコンダクタジャパンでは、長年プロダクトマーケティング、ビジネス開拓職に従事。2016年にソフトウェア業界に転身し、IARシステムズでマーケティングチームマネージャとして活躍。2021年に当社入社後、事業部長、執行役員を経て2023年より取締役、エンベデッド第3事業部長 兼 R&D部長 兼 マーケティング&コミュニケーション部長。豊富なグローバルビジネス経験とB2Bマーケティングの知見が強み。

- 株式会社ラック
- 新規事業開発部
- 部長
- 又江原 恭彦 氏
セッション概要
B6-2 特別講演
実証・研究から見えてきた屋外IoTの課題と今後の取組
IoTには当然様々な分野があります。今回は屋外に設置する世界におけるIoTについて、弊社が取り組んできた実証・研究のご紹介を兼ね、サイバーセキュリティの観点に限らず、そこから見えてきた課題と、今後の取組についてご説明します。
講師

- 又江原 恭彦 氏
- 株式会社ラック
- 新規事業開発部
- 部長
国内各地域の安心・安全なデジタル化、IoT化を推進するためのプラットフォームサービス、地域事業創出を目指した「smart town事業」の実現を目指して活動中。
1997年 ラックに入社。セキュリティ事業の創業期より社内外の各種サイバーセキュリティ事業に従事。
2011年 サイバーセキュリティ事業の中部地区担当の後、セキュリティコンサルティング部門を担当。
2018年 新規事業開発事業責任者。「smart town事業」を推進。現在に至る。
- ナビゲーター
- 株式会社ユビキタスAI
- マーケティング&コミュニケーション部
- 澤田 和臣氏
- ナビゲーター
- 横浜国立大学 先端科学高等研究院 上席特別教授/
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 フェロー
- 松本 勉

- 株式会社SCU
- 代表取締役
- 植村 泰佳 氏
セッション概要
A7 ソリューション講演
セキュアIP=SCUを搭載した製品「セキュリティアダプター」の開発
国プロSIP第1期、第2期を通じて、横浜国大、東大、神戸大、東北大、奈良先端大、電子商取引安全技術研究組合(ECSEC、当時)そのほかいくつかの企業群は、次の特徴を持つセキュアIP=SCUの開発に成功した。
・ECCのHW実装を、きわめて効率の良い手法で実現
・暗号機能の利用にアクセス制御機構を持つ
国プロによる研究開発成果を社会実装するため、2022年ECSECは技術研究組合法に基いて事業会社(株)SCUに改組し、(株)SCUは現在SCU-IPを搭載したSoCや、それを内蔵した汎用セキュリティ製品「セキュリティアダプター」を開発し、販売しようとしている。
講師

- 植村 泰佳 氏
- 株式会社SCU
- 代表取締役
1952年 東京生まれ
1977年 慶應義塾大学卒業
1977-1994年 サッポロビール株式会社に勤務
2000年 電子商取引安全技術研究組合(ECSEC)を設立
2000-2022年 ECSEC常務理事、専務理事、理事長
情報セキュリティの研究、コモンクライテリア、CMVP等の標準化活動、ハードウェアセキュリティ関連の各種研究開発に従事
2022年 技術研究組合法に基づきECSECを事業会社(株)SCUに改組、代表取締役に就任現在に至る。
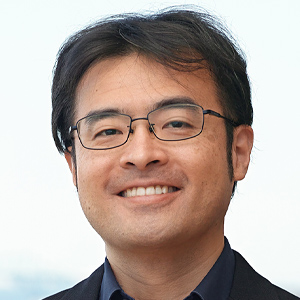
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
- サイバーフィジカルセキュリティ研究センター セキュリティ保証スキーム研究チーム
- 研究チーム長
- 吉田 博隆 氏
セッション概要
A8-1 招待講演
IoT機器に対するセキュリティ規格と保証スキームの動向
IoTの急速な普及と共に、IoT 機器のベンダーが適切な対策を実施し、その効果をユーザーが納得するための仕組みの構築がグローバルに進められている。多くのIoT機器を対象とし、時間的・金銭的なコストを抑えつつ、いかに評価・認証を行うか、が課題となってきている。本発表では、IoT 機器に対するSESIP等のセキュリティ規格、それに基づくセキュリティ保証スキームに関する動向を紹介する。
講師
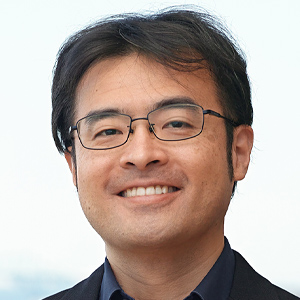
- 吉田 博隆 氏
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
- サイバーフィジカルセキュリティ研究センター セキュリティ保証スキーム研究チーム
- 研究チーム長
2013年 KU Leuven Department of Electrical Engineering 博士課程修了。
2001-2015年に日立製作所研究員、2016年より産業技術総合研究所主任研究員。
2018年11月より産業技術総合研究所 サイバーフィジカルセキュリティ研究センター セキュリティ保証スキーム研究チーム長。セキュリティ保証スキームとIoT向け暗号技術に関する研究に従事。

- 総務省
- サイバーセキュリティ統括官室
- 企画官
- 西村 卓 氏
セッション概要
B8-1 招待講演
サイバーセキュリティ政策の動向
国内外におけるランサムウェア、システム障害や改ざん等、さらには安全保障にも影響を及ぼしかねないサイバー攻撃など、サイバー空間における脅威が高まっている。
社会的に甚大な影響を及ぼすサイバー攻撃事案が増加する中、総務省では近年のサイバー攻撃に関する傾向や社会的なインパクトの大きさなどを踏まえ、こうした脅威への取り組みを進めており、その概要について紹介する。
講師

- 西村 卓 氏
- 総務省
- サイバーセキュリティ統括官室
- 企画官
2000年総務省入省。テレコム分野で電波、放送に関する制度や技術についての施策推進や諸外国との国際課題の解決に長年従事し、2024年7月より現職。

- トヨタ自動車株式会社
- 情報通信企画部InfoTech-IS
- 主査
- 小熊 寿 氏
セッション概要
A8-2 特別講演
Vision of Automotive CTF Event “Hack Festa”
トヨタ自動車、Toyota Motor North America, Inc.、およびToyota Tsusho Systems US, Inc.は共同でCapture The Flagイベントを企画し、2022年から「Hack Festa」を毎年開催している。コロナ過の最中から始まったHack Festaは様々な環境要因を考慮し、トヨタが開発した自動車向けセキュリティテストベッド「PASTA for Education」および「RAMN」を含むオープンソース技術を利用し実現している。本講演では自動車業界におけるHack Festaの位置づけ、および今後の進め方について述べる。
講師

- 小熊 寿 氏
- トヨタ自動車株式会社
- 情報通信企画部InfoTech-IS
- 主査
2002年3月、電気通信大学大学院 電気通信研究科 情報工学専攻 博士後期課程修了及び博士(工学)の学位取得。2007年11月、株式会社トヨタIT開発センターに入社。2019年4月、吸収合併のためトヨタ自動車株式会社へ転籍。入社以来、自動車のサイバーセキュリティに関する研究開発および標準化活動に従事し、現在に至る。

- エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
- 情報セキュリティ部
- 須藤 年章 氏
セッション概要
B8-2 特別講演
電気通信事業者によるサイバー攻撃への効果的な対策実現のためのボットネット実態調査とその対策
20年以上前に初期のボットネットが発見されて以降、今現在も時代に合わせた形でボットネットは進化し、DDoS攻撃やスミッシング、ランサムウェアやAPT攻撃など、社会に影響を与えるサイバー攻撃が発生し、個人や企業は直接の被害者にも他者を攻撃するための踏み台にも利用されるような状況が続いている。これまでもさまざまな角度から対策が行われてきたが効果的な対策を打つには課題が多い。今回は総務省「電気通信事業者によるフロー情報分析を用いた効果的なIoTボットネットへの対処手法の調査研究」におけるISPによるC&Cサーバの早期発見によるDDoS攻撃等の未然防止・被害極小化の実現を目指す調査分析からみえてくるボットネットの実態と、その対策に向けての検討状況について紹介する。
講師

- 須藤 年章 氏
- エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
- 情報セキュリティ部
ISPサービス事業の立ち上げから、ISP目線でのセキュリティ対策やマネージドセキュリティサービスを通して様々なカテゴリでのインシデント対応、サイバーセキュリティ対策を行ってきた。最近はICT-ISAC等の活動を通して業界連携したサイバーセキュリティ対策の検討を行っている。
- ナビゲーター
- 横浜国立大学 先端科学高等研究院 上席特別教授/
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 フェロー
- 松本 勉
- ナビゲーター
- 横浜国立大学
- 大学院環境情報研究院および先端科学高等研究院
- 教授
- 吉岡 克成

- University College London
- Electronic & Electrical Engineering
- Dr. Anna Maria Mandalari
セッション概要
K3 基調講演
Safeguarding the Connected World: Prioritizing Security and Privacy in IoT ※英語→日本語 同時通訳あり
As the Internet of Things (IoT) continues to proliferate in our daily lives, concerns about the potential intrusion into our privacy and security have become more prevalent. This talk aims at fostering an IoT ecosystem that prioritizes user privacy, security, efficiency, and reliability. In an age where smart city initiatives and connected homes are becoming the norm, it is crucial to address the growing challenges associated with IoT devices. This talk will explore strategies and solutions for establishing an IoT environment that places user interests at the forefront. The discussion will encompass cutting-edge approaches to safeguarding data, preserving privacy, and enhancing security in IoT networks, offering a vision of a future where our connected world is safer, more efficient, and truly user-centered.
講師

- Dr. Anna Maria Mandalari
- University College London
- Electronic & Electrical Engineering
Anna Maria Mandalari works as Assistant Professor at University College London (UCL). She is affiliated with the Electronic and Electrical Engineering Department. She is Honorary Research Fellow at the Institute for Security Science and Technology at Imperial College London and expert fellow of the UK SPRITE+ Hub. She is Executive Steering Board Member of the IoT Security Foundation. She has been nominated Member of the Italian Technical Secretariat of the Committee for strategies on the use of AI. She obtained her PhD within the framework of the METRICS project, which is part of the Marie Skłodowska-Curie action, intended for excellent researchers, affiliated with the Carlos III University of Madrid. Her research interests are Internet of Things (IoT), privacy, security, networking and Internet measurement techniques. She studies privacy implications and information exposure from IoT devices. She works on the problem of modelling, designing, and evaluating adaptation strategies based on Internet measurements techniques. In addition to her research, Anna gives invited talks all around the world to promote research and create awareness on security, privacy, and ethical AI. Most of her research experiences have also significantly contributed to several EU-funded research projects and have had a significant influence on media and policymaking. Anna Maria Mandalari is also committed to promoting the interest of young women in STEM subjects.
- ナビゲーター
- 横浜国立大学
- 大学院環境情報研究院および先端科学高等研究院
- 教授
- 吉岡 克成
オンライン展示をご希望の方
-
本フォーラム内でソリューションの展示をいただけるご協賛企業・団体を募集しております。
ご希望・ご検討の方は下記の事務局までお問い合わせください。
協賛プログラムに関する詳細資料やお申込書等をご案内いたします。「IoTセキュリティフォーラム」事務局
E-mail:iotsecurity-forum@impress.co.jp
受付時間 10:00〜18:00(土・日・祝を除く)