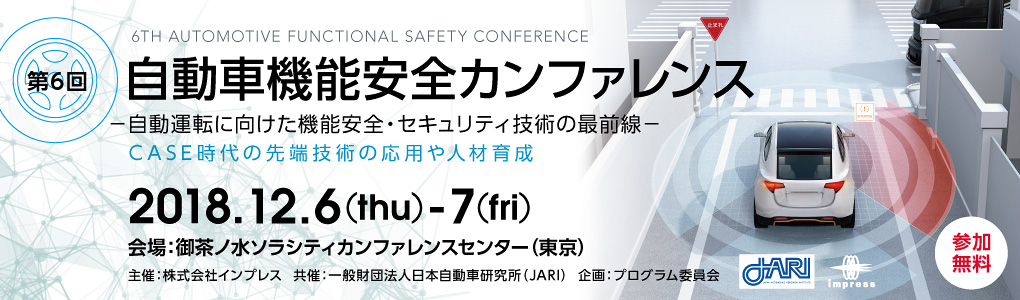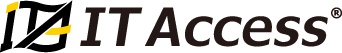タイムテーブル[12/6]
※プログラムは予告なく変更となる場合がありますので、ご了承ください。
10:00~10:10(10分)
オープニングリマークス

自動車機能安全カンファレンス
プログラム委員長
谷川 浩
(一般財団法人日本自動車研究所、ITS研究部部長)
10:10~11:00(50分)
K-1 基調講演
自動運転システムの安全性と人材育成

名古屋大学
未来社会創造機構/大学院情報学研究科
教授
高田 広章
セッション概要
K-1 基調講演「自動運転システムの安全性と人材育成」
この講演では,自動運転システムの安全性に関する考え方を整理した後,安全性を確保・説明する上での課題と取り組みについて紹介する。また、経済産業省の主導で進められている自動走行に関するソフトウェアスキル標準策定の取り組みについても紹介する。
 高田 広章
高田 広章
リアルタイムOSを中心に、組込みシステム設計・開発技術についての研究開発に従事。オープンソースのリアルタイムOS等を開発するTOPPERSプロジェクトを主宰。名古屋大学発ベンチャ企業APTJ(株)を設立し、その代表取締役会長・CTOを務める。博士(理学)。
11:00~11:40(40分)
S-1 特別講演
脅威分析の敷居を下げる脅威分析手法(RWX法)

DNV GL ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社
機能安全部サイバーセキュリティグループ
サイバーセキュリティエキスパート
松並 勝
セッション概要
S-1 特別講演「脅威分析の敷居を下げる脅威分析手法(RWX法)」
自動車業界ではセーフティと同様にサイバーセキュリティも論証が求められる。その論証の基盤となるのが脅威分析である。しかし脅威分析は方法論が整備されておらず、敷居が高く容易なものではなかった。本講演では講師の10年以上にわたる脅威分析の敷居を下げる工夫をまとめた「RWX脅威分析法」を紹介する。
 松並 勝
松並 勝
2000年に自身のWebサイトが踏み台被害に遭ったことから2001年からセキュリティ業界へ。2002年IPAセキュア・プログラミング講座、2012年JSSEC Androidアプリのセキュア設計・セキュアコーディングガイド、2016年脅威分析研究会等、一貫してセキュア開発の普及啓発に取り組む。
11:40~12:40(60分)
昼食休憩および機材セッティング
時間
A会場
B会場
12:40~13:25(45分)
A1-1 招待講演 A会場
システムズエンジニアリングとアシュアランスケースを用いた安全論証の取組み

マツダ株式会社
情報制御モデル開発部
休坂 慎也
セッション概要
A1-1 招待講演「システムズエンジニアリングとアシュアランスケースを用いた安全論証の取組み」
近年の自動車の自動化や電動化などの機能の高度化に伴い、取り巻く社会との関係性も大規模/複雑化、社会的な説明責任を求められる機会も増大する。この変化に対応するため、システムズエンジニアリングとアシュアランスケースの考え方を組み合わせた安全論証手法を構築し、有効性の検証に取組んだ。
 休坂 慎也
休坂 慎也
2007年マツダ(株)入社後、ブレーキ/ステアリング制御システムの量産開発に従事。2016年よりモデルベース・システムズエンジニアリングを活用した次世代自動車制御システムアーキテクチャ構築の研究に従事。
B1-1 招待講演 B会場
JASPAR機能安全WGの取組み~自動運転システムに向けたこれからの機能安全~

一般社団法人JASPAR
機能安全WG
主査
日産自動車株式会社
電子アーキテクチャ開発部
電子信頼性評価グループ
岡田 学

一般社団法人 JASPAR
機能安全WG STAMP/STPAチーム
チームリーダー
(株)日立産業制御ソリューションズ
組込みエンジニアリング事業部 制御システム本部
主任技師
橋本 岳男
セッション概要
B1-1 招待講演「JASPAR機能安全WGの取組み~自動運転システムに向けたこれからの機能安全~」
自動運転車の実現に向けて、クルマとドライバを含めた周辺環境との相互作用はより複雑化が進み、故障に起因しないドライバのミスユースやシステムの性能限界など、さまざまな環境の変化を考慮した機能安全の対応が求められている。規格化が進むSOTIFの動向などを交えながら機能安全WGの取組みについて紹介する。
 岡田 学
岡田 学
機能安全推進部署にて、電気自動車の機能安全アセスメントや社内基準・手法策定に従事。現在、ミスユースや性能限界起因の安全設計プロセス構築に向け、STAMP/STPA普及拡大に取り組んでいる。
 橋本 岳男
橋本 岳男
3G無線通信システムの開発に従事後、車載ネットワークやパワートレイン等の自動車制御システム開発に参画。現在は、自動車メーカ/サプライヤ様向けにMBSEの実践的導入を推進。INCOSE会員
13:25~13:45(20分)
A1-2 企業講演 A会場
開発上流工程への形式検証導入による安全性・信頼性向上

株式会社構造計画研究所
事業開発部 AOR研究室
室長
太田 洋二郎
セッション概要
A1-2 企業講演「開発上流工程への形式検証導入による安全性・信頼性向上」
車載システムの複雑さにより検証が困難になっている。シミュレーションより厳密な検証手法として期待される形式検証は、開発上流工程への適用がより効果的である。本講演では、UML/SysML等によるシステム設計のモデル検査を中心に、STAMP安全分析やセキュリティへの形式検証の適用を提案、またSCDLを活用した安全要求分析を紹介する。
 太田 洋二郎
太田 洋二郎
1987年(株)構造計画研究所に入社以来、通信、製造、物流、防衛等の各分野でモデリング&シミュレーション、最適化業務に従事。現在は、形式検証を中心としてシステム開発における安全性・信頼性向上に取り組み、自動車、鉄道等の各業界で形式検証の導入支援を行っている。
B1-2 企業講演 B会場
複雑化するシステムの機能安全設計におけるMBSE実践適用と効果

株式会社日立産業制御ソリューションズ
組込みエンジニアリング事業部 制御システム本部
主任技師
橋本 岳男
セッション概要
B1-2 企業講演「複雑化するシステムの機能安全設計におけるMBSE実践適用と効果」
車載システムは、安全運転支援機能の急速な進化に伴い、自動車内外の多くのシステムとの連携なくしては成り立たない。しかし、連携は新たなステークホルダを生みその要求も多様化し、開発現場は様々な工夫により機能安全に対応している。
本セッションでは、MBSE適用により複雑なシステム全体を俯瞰し最適な機能安全設計を実現する活用法について紹介する。
 橋本 岳男
橋本 岳男
3G無線通信システムの開発に従事後、車載ネットワークやパワートレイン等の自動車制御システム開発に参画。現在は、自動車メーカ/サプライヤ様向けにMBSEの実践的導入を推進。INCOSE会員。
13:50~14:10(20分)
A1-3 企業講演 A会場
IEC61709、IEC/TR 62380及びSN29500を用いた故障率計算例と比較

株式会社ウェーブフロント
情報数理ソリューション開発部
シニア上級コンサルタント
眞榮平 修
セッション概要
A1-3 企業講演「IEC61709、IEC/TR 62380及びSN29500を用いた故障率計算例と比較」
FMEDAで用いるFIT値計算の信頼性ハンドブックとしてIEC/TR62380が広く使われているが、当該規格は2017年に更新が終了し、IEC61709が後継規格となった。IEC/TR62380での故障率計算の進め方に対し、IEC61709、SN29500を用いる際の変化点と対応について紹介する。
 眞榮平 修
眞榮平 修
1990年にウェーブフロントに入社以来保全システムの開発、保全管理に関するコンサルタントを担当。2009年よりISO26262機能安全、鉄道RAMS、原子力PSA(PRA)における安全性・信頼性評価手法に関する支援やプラント、機器に関する故障分析、信頼性評価の実施及び保全への反映等の支援を担当。
B1-3 企業講演 B会場
準備中
14:10~14:50(40分)
休憩および機材セッティング
14:50~15:35(45分)
A2-1 招待講演 A会場
車載制御ソフトウェアへの定理証明の適用と課題

株式会社ジェイテクト
ステアリングシステム開発部
主担当
米木 真哉
セッション概要
A2-1 招待講演「車載制御ソフトウェアへの定理証明の適用と課題」
自動運転の実用化に伴い、特定機能の喪失が安全要求の侵害に至る可能性がある。このためソフトウェアに関しても、従来、異常検出時は安全停止としていたものも、最低限の機能維持が必須となる。そこで、ソフトウェアに機能失陥に至る不具合が存在しないことを、定理証明を用いて論証するための試行結果と課題を紹介する。
 米木 真哉
米木 真哉
原子力、化学プラント、鉄道、自動車等の安全関連システムの開発業務に従事。2013年から(株)ジェイテクトにて電動EPSの機能安全サポート業務に当たっている。併せて、ISO 26262の改訂、およびISO/SAE 21434(自動車のサイバセキュリティ)に向けた国内・国際委員会へも参加している。
B2-1 招待講演 B会場
ISO 26262共同研究エンジンWG成果報告
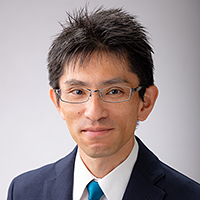
株式会社デンソー
エレクトロニクス製品基盤技術部
課長
佐々木 恵司

株式会社本田技術研究所 4輪R&Dセンター
統合制御室 第4ブロック
主任研究員
落合 志信
セッション概要
B2-1 招待講演「ISO 26262共同研究エンジンWG成果報告」
エンジンシステムにおけるISO 26262適用時の規格解釈について、WGで議論した内容、解釈例などについて報告する。
今回は、「ISO 26262適用済システム変更開発の勘所と検証」と「Latentフォールトの取組みに関する規格解釈と検討事例」について、報告する。
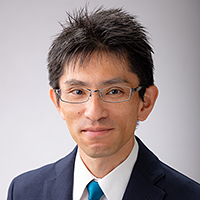 佐々木 恵司
佐々木 恵司
2002年 株式会社デンソーに入社。エンジン/パワートレインの制御ソフトウェアの開発に従事。ISO 26262共同研究エンジンWGにおいてはマイコンタスクフォースにて活動中。
 落合 志信
落合 志信
電装領域でのEng ECU開発業務を経てエンジン、HEV、バッテリEV等Power Plantのシステム制御開発に従事
2011年ISO26262の波と共にPP全体の機能安全活動推進
エンジン、HEV、EV、FCEV系の安全機構設計を担当
現在、同領域のISO26262アセッサー
15:35~15:55(20分)
A2-2 企業講演 A会場
形式検証を応用した自動運転プログラムの安全確保手法

AdaCore
シニアソフトウエアエンジニア
Kanig Johannes
セッション概要
A2-2 企業講演「形式検証を応用した自動運転プログラムの安全確保手法」
SPARKPro形式検証手法は、長年、航空宇宙等の高信頼性ソフトウエアを搭載した機器で利用されている。プログラムの確からしさを検証後、コンパイルして実機で動作可能である。その技術をAI等で構成される自動運転(レベル4)プログラムの監視システムへ応用し、安全性を確保する手法を紹介する。
※講演言語:英語
 Kanig Johannes
Kanig Johannes
AdaCore社でSPARKPro形式検証手法の開発に携わっている。2011年フランスParis-Sud大学で形式証明に関する博士号取得
提供:アイティアクセス株式会社
B2-2 企業講演 B会場
調整中
15:55~16:10(15分)
休憩および機材セッティング
16:10~17:40(90分)
P-1 パネルディスカッション A会場
実用化に向けて動き出した自動運転~協調と共創の戦略~
パネリスト

名古屋大学
未来社会創造機構/大学院情報学研究科
教授
高田 広章

一般社団法人日本自動車工業会
エレクトロニクス部会 電子安全性分科会
分科会長
川名 茂之

マツダ株式会社
統合制御システム開発本部
上席研究員
久保 敬也

日立オートモティブシステムズ株式会社
技術開発本部
電子プラットフォーム技術統括 主管技師長
宮崎 義弘

一般財団法人日本自動車研究所
ITS研究部
部長
谷川 浩
モデレーター

独立行政法人情報処理推進機構
社会基盤センター
調査役
田丸 喜一郎
セッション概要
P-1 パネルディスカッション「実用化に向けて動き出した自動運転~協調と共創の戦略~」
調整中
パネリスト
 高田 広章
名古屋大学 未来社会創造機構/大学院情報学研究科 教授
リアルタイムOSを中心に、組込みシステム設計・開発技術についての研究開発に従事。オープンソースのリアルタイムOS等を開発するTOPPERSプロジェクトを主宰。名古屋大学発ベンチャ企業APTJ(株)を設立し、その代表取締役会長・CTOを務める。博士(理学)。
高田 広章
名古屋大学 未来社会創造機構/大学院情報学研究科 教授
リアルタイムOSを中心に、組込みシステム設計・開発技術についての研究開発に従事。オープンソースのリアルタイムOS等を開発するTOPPERSプロジェクトを主宰。名古屋大学発ベンチャ企業APTJ(株)を設立し、その代表取締役会長・CTOを務める。博士(理学)。
 川名 茂之
一般社団法人日本自動車工業会 エレクトロニクス部会 電子安全性分科会 分科会長
自工会電子安全性分科会長として、車載電気電子システムの安全設計基盤技術の業界活動に従事。同時に自技会機能安全分科会幹事、ISO/TC22/SC32/WG8の国際標準のエキスパート、名古屋大学非常勤講師。トヨタ自動車(株)。
川名 茂之
一般社団法人日本自動車工業会 エレクトロニクス部会 電子安全性分科会 分科会長
自工会電子安全性分科会長として、車載電気電子システムの安全設計基盤技術の業界活動に従事。同時に自技会機能安全分科会幹事、ISO/TC22/SC32/WG8の国際標準のエキスパート、名古屋大学非常勤講師。トヨタ自動車(株)。
 久保 敬也
マツダ株式会社 統合制御システム開発本部 上席研究員
1984年マツダ(株)入社、主に車両電装品の開発に携わり、北米・中国に駐在しての現地開発を経験。
久保 敬也
マツダ株式会社 統合制御システム開発本部 上席研究員
1984年マツダ(株)入社、主に車両電装品の開発に携わり、北米・中国に駐在しての現地開発を経験。
2008年から現在まで先進安全技術(ADAS)及び自動運転技術の開発に関わる。
ISO26262を含む電装品・制御の安全開発の社内リーダを長年担当。
自工会電子安全性分科会副分科会長
 宮崎 義弘
日立オートモティブシステムズ株式会社 技術開発本部 電子プラットフォーム技術統括 主管技師長
日立製作所(株)入社後、制御用コンピュータの開発などを担当。現在、日立オートモティブシステムズ(株)技術開発本部にて、車載制御システムの電子プラットフォーム技術開発に従事。当社内の機能安全対応の技術推進取り纏めを担当。JARI/ISO 26262運営委員会委員、JASPAR/機能安全WG技術アドバイザ。
宮崎 義弘
日立オートモティブシステムズ株式会社 技術開発本部 電子プラットフォーム技術統括 主管技師長
日立製作所(株)入社後、制御用コンピュータの開発などを担当。現在、日立オートモティブシステムズ(株)技術開発本部にて、車載制御システムの電子プラットフォーム技術開発に従事。当社内の機能安全対応の技術推進取り纏めを担当。JARI/ISO 26262運営委員会委員、JASPAR/機能安全WG技術アドバイザ。
 谷川 浩
一般財団法人日本自動車研究所 ITS研究部 部長
1983年トヨタ自動車に入社、エンジン制御用電子システム,センサー開発、車内LAN・ソフトPFの国際標準化活動等に従事。自動車メーカー・サプライヤー連携テーマの企画、共同開発やビジネスの仕組みつくり、標準化活動などを幅広く経験し、2004年にはトヨタ自動車代表としてJaspar設立にも参画。
谷川 浩
一般財団法人日本自動車研究所 ITS研究部 部長
1983年トヨタ自動車に入社、エンジン制御用電子システム,センサー開発、車内LAN・ソフトPFの国際標準化活動等に従事。自動車メーカー・サプライヤー連携テーマの企画、共同開発やビジネスの仕組みつくり、標準化活動などを幅広く経験し、2004年にはトヨタ自動車代表としてJaspar設立にも参画。
近年では先進的な制御システム開発や開発の仕組み作りなどに従事。2013年5月から日本自動車研究所に籍を置き自動走行関係事業の企画ならびに研究推進に取り組み、現在に至る。
モデレーター
 田丸 喜一郎
独立行政法人情報処理推進機構 社会基盤センター 調査役
1981年慶應義塾大学工学研究科博士課程修了(工学博士)。同年、株式会社東芝入社。
田丸 喜一郎
独立行政法人情報処理推進機構 社会基盤センター 調査役
1981年慶應義塾大学工学研究科博士課程修了(工学博士)。同年、株式会社東芝入社。
半導体技術研究所、本社技術企画室などを経て、2004年より独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の活動に従事。
現在、IPA社会基盤センター調査役。九州工業大学情報工学部客員教授、一般社団法人ディペンダビリティ技術推進協会(DEOS協会)副理事長、LoRa Alliance™ Japan代表などを務める。
B会場
サテライト会場(A会場の内容を中継して、プロジェクタで投影致します。)