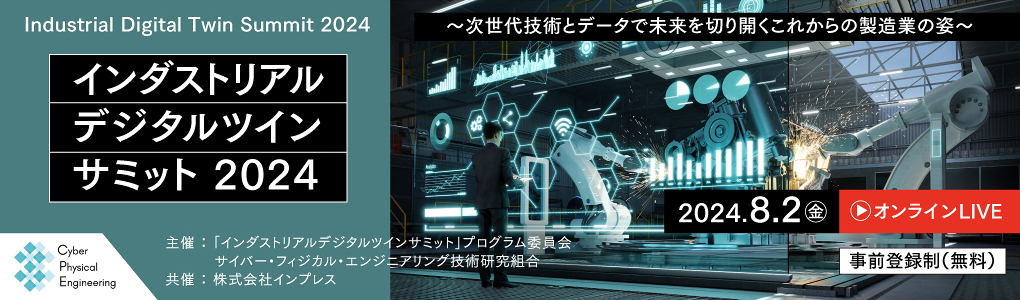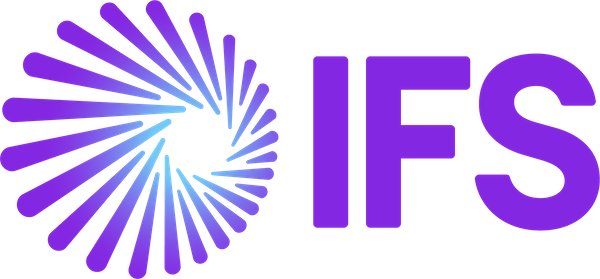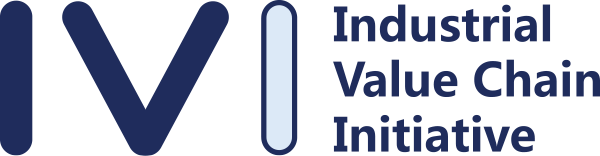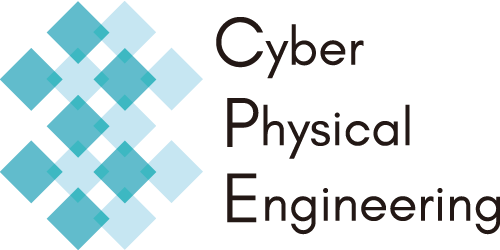8月2日(金)
講演プログラム
9:30-9:35
OP
オープニングリマークス
開会のご挨拶
プロフィール
プロフィール
1986年京都大学精密工学科卒業、1988年京都大学大学院工学研究科精密工学専攻修士課程修了、(株)豊田中央研究所入社。1998年ミシガン大学工学部機械応用力学学科博士課程修了。Ph.D.取得。2002年(株)豊田中央研究所退社、京都大学工学研究科 助教授、2007年同准教授、2009年同教授、現在に至る。
9:35-10:20
K-1
基調講演
「モビリティDX戦略」を通じた我が国の競争力強化に向けて
10:20-10:50
K-2
特別講演
Digital Twins in a PLM context
10:50-11:00
Kブロックに関するQ&Aセッション
11:00-11:10
休憩
Aトラック
Bトラック
11:10-11:35
A-1
招待講演
航空機エンジン
故障予測
ライフサイクル
民間航空機エンジンのトレンドモニタリング
11:35-12:00
A-2
ソリューション講演
航空機エンジンのデジタルツインと部品寿命の最適化ソリューション
12:00-12:10
Aブロックに関するQ&Aセッション
12:10-12:20
休憩
12:20-12:45
B-1
招待講演
12:45-13:10
B-2
ソリューション講演
エッジコンピューティング最新事例から見る製造現場のデータ利活用 課題解決のポイント
13:10-13:20
Bブロックに関するQ&Aセッション
13:20-13:30
休憩
13:30-13:55
C-1
招待講演
製造デジタルツインと性能予測技術の融合について一考察
13:55-14:20
C-2
ソリューション講演
物理ベースのモデルを使用した生産技術・設備保全のためのデジタルツイン
14:20-14:30
Cブロックに関するQ&Aセッション
14:30-14:40
休憩
14:40-15:05
D-1
招待講演
トポロジー最適化
構造最適化
画像処理
ユーザの嗜好を考慮したトポロジー最適化技術に関する基礎的研究
15:05-15:30
D-2
ソリューション講演
物理シミュレーションとデータ解析で最適化するデジタルツイン
15:30-15:40
Dブロックに関するQ&Aセッション
15:40-15:50
休憩
15:50-16:15
E-1
招待講演
実測データを活用したCAEによる解析モデルの精緻化と製品開発プロセスの変革
16:15-16:40
E-2
ソリューション講演
ITとOTの融合はなぜ必要か?製造DXで考えるべき論点
16:40-16:50
Eブロックに関するQ&Aセッション
16:50-17:00
休憩
17:00-18:00
P-1
パネルディスカッション
18:00-18:10
CL
クロージングリマークス
Coming soon