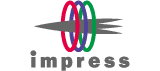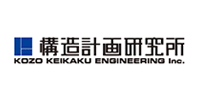本イベントは終了しました。ご来場誠にありがとうございました。
テーマカテゴリー
過去のデータを用いてのCAE、簡易モデルを用いてのCAE、FOA、1DCAE
開発初期、CADデータ作成までの期間を概念設計フェーズと定義し、この間、如何に有効な検討をするかを議論する。これまで車体、シャーシ等を対象に、FOA(First Order Analysis)に代表される簡易モデルを用いての検討が提案されている。ここでは一般的製品開発を対象に提案されている1DCAE(内閣府プロジェクト)の概念も参考に議論を進める。自動車開発の場合、過去のモデルの情報があるのでその情報を有効に活用する。対象を拡げ、車体、シャーシ以外にも展開し、その取り分の明確化を目指す。
鋳造・鍛造・プレス成形・接合など加工に関するCAE全般(ロボティクスは含まない)
製造品質向上、製造コスト低減および生産準備期間短縮を目的に、鋳造・鍛造・プレス成形など生産加工におけるCAEの利活用が進んでいる。また、生産加工CAEと設計CAEをコンカレントに行うことで、製造要件を考慮した手戻りの少ない設計も可能になってきた。本カテゴリでは、生産加工CAEに関する最先端の技術について取り上げる。
ADAS(先進運転支援システム)の開発をサポートするシミュレーションや実験に関するCAE技術全般
先進諸国では安全規制強化に伴い、運転支援という側面から新たな走行制御 デバイスの搭載標準化が近年進められている。 また、それに応じて、デザインフェーズにおける各システムの機能・信頼性・走行性能等の考察や検討を支援するシミュレーション技術とフィジカルフェーズにおけるXiLのような実機テストの一部を代替する実験技術も飛躍的に進化している。 本カテゴリーではADASに適用されるこれらの技術について論議する。