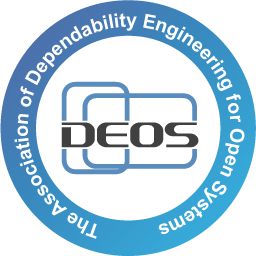本イベントの参加登録受付は終了いたしました。多数のご登録を頂き誠にありがとうございました。
タイムテーブル[12/5]
※プログラムは予告なく変更となる場合がありますので、ご了承ください。
9:30~9:40(10分)
オープニングリマークス

自動車機能安全カンファレンス プログラム委員長
一般財団法人日本自動車研究所
ITS研究部
部長
谷川 浩
9:40~10:30(50分)
K-1 基調講演
すべての人に移動の自由をー 未来のモビリティ社会に向けた自動運転開発の取組み ー

トヨタ自動車株式会社
先進技術開発カンパニー 先進安全領域
領域長
鯉渕 健
セッション概要
K-1 基調講演「すべての人に移動の自由を ー 未来のモビリティ社会に向けた自動運転開発の取組み ー」
未来のモビリティ社会を支える技術として期待が高まる自動運転。近年、実現に近づいていると同時に、グローバルな開発競争は更に激化している。 本講演では、トヨタの自動運転技術開発の取組みを示し、技術の実用化に向けた課題や社会へのインパクトについて語る。
 鯉渕 健 氏
鯉渕 健 氏
1993年 トヨタ自動車に入社。車両運動性能開発等を経て、シャシー制御開発を担当。さらにパワートレイン系統合制御他幅広く制御システムの開発を経験。そして、2014年より自動運転技術、先進安全技術の開発を担当。現職は、トヨタ自動車 先進技術開発カンパニー 先進安全領域 領域長、及びトヨタ・リサーチ・インスティテュート・アドバンスト・デベロップメント株式会社 取締役 CTOを務める。
10:30~11:10(40分)
S-1 特別講演
半導体設計からシステム設計まで:
シノプシスが提供するオートモーティブ・ソリューションとその機能安全対応

日本シノプシス合同会社
ベリフィケーション・グループ
シニア・マネージャー FAE
中野 淳二
セッション概要
S-1 特別講演「半導体設計からシステム設計まで:シノプシスが提供するオートモーティブ・ソリューションとその機能安全対応」
近年、車載電子システムは車の設計・検証コストの大部分を占めてきており、機能安全の側面でも重要な役割を果たしている。自動運転の実用に向け、先進の複雑なアルゴリズムを実装すること求められ、クラウドコンピューティングで使われるような巨大な演算リソースが必要となってきている。シノプシスは半導体設計からシステム設計まで広範なツールを提供している。それらの設計ツールがどのように車載で機能安全に対応しているか、半導体のテストやセキュリティ、システム設計と様々な角度から紹介する。
 中野 淳二 氏
中野 淳二 氏
八重洲無線株式会社において無線機のデジタル化に関する研究に従事。1995年より日本シノプシスにおいて、バーチャル・プロトタイプ、アルゴリズム設計、高位合成など上流系の製品を24年にわたり担当。自動車分野におけるバーチャル・プロトタイプの適用に関するプロジェクトを14年以上にわたり担当。
11:10~12:40(90分)
お昼休憩および会場転換
C-1 企業講演 C会場 11:30~11:45(15分)
車載ソフトウェア開発におけるトレーサビリティの課題と最新ツール活用事例

株式会社DTSインサイト
第一事業本部 第一事業部 ソフトウェアサービス部 ソフトウェアサービス1課
課長
松田 尚樹
セッション概要
C-1 企業講演「車載ソフトウェア開発におけるトレーサビリティの課題と最新ツール活用事例」
機能安全対応、AutomotiveSPICEでの開発プロセスにおいては、要件管理、変更管理、MDD/MBD開発、セキュリティ対応など、各プロセスでトレーサビリティ情報を構築、利用し高品質のソフトウェアを提供することが求められる。トレーサビリティ構築における課題と最新ツール活用事例をご紹介する。
 松田 尚樹 氏
松田 尚樹 氏
1999年に株式会社DTSインサイト(旧横河ディジタルコンピュータ株式会社)に入社し、インサーキットエミュレータ advice等の開発ツールの提案、販売に従事。
2014年以降は成果物のトレーサビリティ管理を中心に自動車関連企業へソフトウェア開発支援のためのツール/プロセス提案を行っている。
C-2 企業講演 C会場 12:10~12:25(15分)
DEOS協会活動2019年概要~自動運転技術領域におけるDEOSの役割~

一般社団法人 ディペンダビリティ技術推進協会
D-ADD部会
主査
永山 辰巳
セッション概要
C-2 企業講演「DEOS協会活動2019年概要 ~自動運転技術領域におけるDEOSの役割~」
オープンシステム・ディペンダビリティ達成のガイダンスが昨年、IEC62853として国際標準として制定された。オープンシステムを対象としたこの日本発の国際規格は、今後ますます注目されて行くと思われる。自動運転の対象はオープンシステムであり、そこではシステムが予測不可能な事態に直面する可能性を想定した設計・開発・運用ポリシーが求められている。DEOS協会の部会の一つである自動車応用部会とD-ADD(合意記述データベース)部会では、OEM/Tier1/Tier2の方々と共に、目前の具体的な課題解決の議論を通して、自動運転時代のシステムのあるべき姿を探求している。
 永山 辰巳 氏
永山 辰巳 氏
オープンシステムディペンダビリティ、「変化しつづけるシステムのサービス継続と説明責任の全う」ための合意記述データベースを開発し、産業界への応用普及を推進中。
一般社団法人ディペンダビリティ推進協議会(通称DEOS協会) D-ADD(合意記述データベース)部会主査
IEC/TC56国内委員
株式会社Symphony代表
時間
A会場
B会場
12:40~13:20(40分)
A1-1 招待講演 A会場
自動運転におけるAIのテスト・AIによるテスト

国立情報学研究所
アーキテクチャ科学研究系
准教授
石川 冬樹
セッション概要
A1-1 招待講演「自動運転におけるAIのテスト・AIによるテスト」
機械学習を用いデータから振る舞いを構築したAIシステムは、従来ソフトウェアとは異なる不確かさを持つ.これに対し、AIによるテスト技術とも呼べるアプローチに基づき、特に自動運転を対象としたテスト技術が盛んに取り組まれている。本講演ではこれらAIのテスト・AIによるテストに関する研究動向を紹介する。
 石川 冬樹 氏
石川 冬樹 氏
国立情報学研究所 アーキテクチャ科学研究系 准教授 および先端ソフトウェア工学・国際研究センター 副センター長。
日本ソフトウェア科学会機械学習工学研究会 主査、AIプロダクト品質保証コンソーシアム 副運営委員長。
B1-1 招待講演 B会場
自動運転に向けたJASPAR機能安全WGの取組み~ガイド・手法開発と人財育成~

一般社団法人JASPAR
機能安全WG
主査
岡田 学

一般社団法人JASPAR
機能安全WG
副主査
河野 文昭
セッション概要
B1-1 招待講演「自動運転に向けたJASPAR機能安全WGの取組み ~ガイド・手法開発と人財育成~」
自動運転の機能安全開発に向けて、ISO26262:2018へのガイド(ソフト、ハード、通信)とSOTIF ISO PAS 21448 への手法開発(安全分析手法、安全アーキテクチャ設計/評価)、中長期的な人材育成(システム思考、システムズエンジニアリング、アーキテクチャ記述)の取組みについて紹介する。
 岡田 学 氏
岡田 学 氏
自動運転に向け3年前からJASPAR活動をストレッチ。安全性論証はSOTIF ISO PAS 21448には不可欠で、さらにSTAMP/STPAはミスユース分析の効果をSAEに提案、主機能の捉え方として安全設計デザインパターンと一通りの材料が揃いつつある。これらを組合せ現場適用フェーズへ移行する。
 河野 文昭 氏
河野 文昭 氏
JASPAR機能安全WGの副主査として5年目を迎える。本年は、自動運転および先進運転支援に関わる機能安全(2nd Edition)、SOTIF、サイバーセキュリティといった重要トピックに向きあい、これらの開発に有効な5つの協調領域活動をWG参加企業様と連携して精力的に展開中。
13:25~13:45(20分)
A1-2 企業講演 A会場
自動運転サービスの安全性を担保する考え方(仮)

株式会社OTSL
プロセス事業部
事業部長
山本 輝俊
セッション概要
A1-2 企業講演「自動運転サービスの安全性を担保する考え方(仮)」
自動運転車を用いた様々なサービスが検討されている。サービスは単に実現手段を示すだけでなく、何故それで良いかを示す根拠を示す必要がある。そこで今回は、企画時に創発されたアイディアがサービスとして成立するかどうか、安全性など導出理由を踏まえて計画・検証するための考え方を示す。
 山本 輝俊 氏
山本 輝俊 氏
機能安全・セキュリティを含む開発プロセスに関する支援業務に従事(機能安全・セキュリティの講習・教育のコンテンツ作成/講師、プロセス改善/成果物作成支援など)
一般社団法人JASPAR機能安全WG ソフトウェアチームリーダ
IoT住宅における機能安全の国際標準策定WG オブザーバー件講師
B1-2 企業講演 B会場
テストに依存しない,ソフトウェア欠陥を防ぐ効果的・効率的な形式検証の始め方~SPARKを用いて~

株式会社ニルソフトウェア
代表取締役
伊藤 昌夫
(提供:アイティアクセス株式会社)
セッション概要
B1-2 企業講演「テストに依存しない,ソフトウェア欠陥を防ぐ効果的・効率的な形式検証の始め方 ~SPARKを用いて~」
形式検証とは「数学的なモデルを用いプログラムが仕様と合っているかを確認する」ことで、テストと相補的である。テストは多大な工数を必要とし、モレをつねに意識する必要がある。形式検証では、同様のことは生じない。ただ、取り組むには敷居が高い。今回、SPARK を用いることで、形式検証が容易となることを示す。
 伊藤 昌夫 氏
伊藤 昌夫 氏
自動車会社,航空宇宙関連会社を経て,ニルソフトウェアを設立.安全性に着目したソフトウェアツールを開発している.社会を背景としたシステムの安全性に興味を持つ.
(提供:アイティアクセス株式会社)
13:50~14:10(20分)
A1-3 企業講演 A会場
Designing mixed criticality systems for safety and security requirements
安全性とセキュリティの要件を満たすミックスクリティカルシステム設計
※講演言語:日本語

Green Hills Software
Advanced Products
FAE
リエゴディジョス エルマー
セッション概要
A1-3 企業講演「Designing mixed criticality systems for safety and security requirements 安全性とセキュリティの要件を満たすミックスクリティカルシステム設計 ※講演言語:日本語」
近年はAI, OTA, V2X の機能安全に対しての要求も高まっており、コネクテッドカーのセキュリティ機能は後付け的な機能ではなく、しっかりとシステムの根幹として組込まれていなければならない。このプレゼンテーションでは厳しい機能安全基準を満たす為のキーファクターとなる元々航空関連制御システム向けの安全仕様を満たす目的で作られたINTEGRITYリアルタイムオペレーティングシステム(RTOS)について説明をする。
 リエゴディジョス エルマー 氏
リエゴディジョス エルマー 氏
日本のFAE。グリーンヒルズソフトウェアに2018年入社。20年に及ぶ組込み業界での経験があり、多くのカスタマーの組込み開発をサポートしてきた。自動車業界だけでなく、工業、メディカルなど様々なマーケットにおいて顧客をサポートしている。
B1-3 企業講演 B会場
SEooCとしての電動化システム開発と安全論証 事例発表

ビジネスキューブ・アンド・パートナーズ株式会社
コンサルティング事業部
ディレクター
土屋 友幸

株式会社ケーヒン
開発本部電動技術統括部PCU開発部第一課
主任
鷺谷 吉則
セッション概要
B1-3 企業講演「SEooCとしての電動化システム開発と安全論証 事例発表」
自動車の電動化に伴い、ビジネス拡大や新規参入時のコンセプトとして、異なるOEMからの安全要求または、異なる用途を想定して製品開発することが、ビジネス拡大の鍵となる。本講演では、電動化システム製品を事例に、背景によらない製品開発とその安全論証のコツをTier1サプライヤ様と共同で紹介する。
 土屋 友幸 氏
土屋 友幸 氏
前職のブレーキシステムサプライヤにおいて、機能安全対応プロセスの構築、システムエンジニアリング部門の立ち上げ、システムエンジニアリング手法論の実装を経験、現在はビジネスキューブ・アンド・パートナーズ株式会社でその経験を強みとしたコンサルティングを展開している。
 鷺谷 吉則 氏
鷺谷 吉則 氏
ケーヒン製MotorECUのハード開発を経て、システム設計エンジニアとしてケーヒン製PCUのシステム設計を担当。
機能安全プロセス(Part4、Part5)の構築を行い、機能安全技術者としても自社製PCUの安全性能へ貢献。
14:10~14:50(40分)
休憩および機材セッティング
14:50~15:30(40分)
A2-1 招待講演 A会場
ソフトウェアコンポーネント間のFFIの実現手法と分析事例

名古屋大学
未来社会創造機構/大学院情報学研究科
教授
高田 広章
セッション概要
A2-1 招待講演「ソフトウェアコンポーネント間のFFIの実現手法と分析事例」
異なる安全度水準(ASIL)のソフトウェアコンポーネントを同一のマイコンに載せる場合,コンポーネント間でFFI(Freedom From Interfarence)を実現することが求められる。この講演では,ソフトウェアコンポーネント間のFFIの実現アプローチを概観し,FFIの実現を支援するソフトウェアプラットフォームの分析事例について述べる。
 高田 広章 氏
高田 広章 氏
リアルタイムOSを中心に、組込みシステム設計・開発技術についての研究開発に従事。オープンソースのリアルタイムOS等を開発するTOPPERSプロジェクトを主宰。名古屋大学発ベンチャ企業APTJ(株)を設立し、その代表取締役会長・CTOを務める。博士(理学)。
B2-1 招待講演 B会場
機能安全分野横断(水平)規格関連の最新動向(機能安全とセキュリティの両立のためのフレームワーク)

株式会社日立製作所
研究開発グループ 制御イノベーションセンタ
主管研究員
金川 信康
セッション概要
B2-1 招待講演「機能安全分野横断(水平)規格関連の最新動向(機能安全とセキュリティの両立のためのフレームワーク)」
本報告では機能安全関連分野横断(水平)規格の最新動向について紹介する。工業用プロセス計測制御及びオートメーションの安全については機能安全規格IEC 61508が1999年-2000年にかけて制定され、現在では水平規格として他の分野でも幅広く参照されている。セキュリティについてもIEC 62443シリーズとして現在順次規格化が進められている。さらに近年になって機能安全とセキュリティの両立のためのフレームワークIEC TR63069が制定されている。さらにこれらの規格動向に対応するための報告者らの取り組みについて紹介する。
 金川 信康 氏
金川 信康 氏
IEC TC65 SC65A/MT61508、WG17、WG20国際エキスパート。
日本信頼性学会前会長、電子情報通信学会フェロー、IFIP TC.10, WG.10.4各メンバー、情報処理学会IFIP日本代表委員。IEEE Senior member,電気学会会員。博士(工学)。
著書(分担執筆)「信頼性ハンドブック」/「新版・信頼性ハンドブック」(日科技連出版社,1997年度/2014年度年日経品質管理文献賞)、”Dependability in Electronic Systems”, Springer (2010)他。
15:35~15:55(20分)
A2-2 企業講演 A会場
形式言語モデルを活用した効率的なソフトウェア開発

株式会社IDAJ
解析技術2部
リーダー
栗原 康一
セッション概要
A2-2 企業講演「形式言語モデルを活用した効率的なソフトウェア開発」
ソフトウェアの複雑化にともない,検証工程の効率化が益々重量となっている。本講演では,ソフトウェアの振る舞いをモデル化するモデリング言語に形式言語を用いることにより可能となる検証工程の効率化について紹介する。
 栗原 康一 氏
栗原 康一 氏
2019年株式会社IDAJに入社。機能安全認証に特化したモデルベール開発ソリューション関連業務に従事。
B2-2 企業講演 B会場
大規模化、複雑化したソフトウェアでの性能解析~重要なポイントと解析手法の解説~

イーソルトリニティ株式会社
営業部
部長
仮屋 義明
セッション概要
B2-2 企業講演「大規模化、複雑化したソフトウェアでの性能解析 ~重要なポイントと解析手法の解説~」
マルチコアマイコンの採用やソフトウェア構造の複雑化により、機能安全対応が必要なソフトウェア性能要求を実現する為の難易度は非常に高くなっている。今回のセッションでは、複雑化したソフトウェアの性能測定や解析のユースケースと高性能ソフトウェアを開発する為に必要となる重要なポイントや対応手法について、ユーザー様の事例を交えながら解説する。
 仮屋 義明 氏
仮屋 義明 氏
1991年に株式会社DTSインサイト(旧横河ディジタルコンピュータ株式会社)に入社し、情報系システム構築業務に従事。
2000年以降は組込みソフトウェアツールの製造販売業務を担当し、情報家電や自動車関連ソフトウェア開発支援活動を実施。
2018年5月にイーソルトリニティに入社し自動車関連企業向けのツール販売、支援業務に従事。
16:00~16:20(20分)
A2-3 企業講演 A会場
上流設計品質向上を促進するモデルベースの実践的な形式検証

株式会社構造計画研究所
事業開発部 AOR研究室
室長
太田 洋二郎
セッション概要
A2-3 企業講演「上流設計品質向上を促進するモデルベースの実践的な形式検証」
車載システム開発が大規模、複雑化する中、詳細モデルより上流のシステムレベル/抽象モデルでの振る舞いの明確化、検証が重要になる。
本講演では自社内もしくはOEM、サプライヤ間で形式検証が実行可能なUML/SysMLモデルを共有し、フロントローディングによる品質、安全性、開発効率の向上を実現する手法を紹介する。
 太田 洋二郎 氏
太田 洋二郎 氏
1987年(株)構造計画研究所に入社以来、通信、製造、物流、防衛等の各分野でモデリング&シミュレーション、最適化業務に従事。現在は、形式検証を中心としてシステム開発における安全性・信頼性向上に取り組み、自動車、鉄道、航空宇宙等の幅広い分野で形式検証の導入支援を行っている。
B会場
サテライト会場(A会場の内容を中継して、プロジェクタで投影致します。)
16:20~16:30(10分)
休憩および機材セッティング
16:30~17:30(60分)
P-1 パネルディスカッション A会場
便利で快適なモビリティ社会の未来
パネリスト

トヨタ自動車株式会社
先進技術開発カンパニー 先進安全領域
領域長
鯉渕 健

国際自動車ジャーナリスト
清水 和夫

株式会社アドヴィックス
技術統括部
主査
河野 文昭

自動車機能安全カンファレンス プログラム委員長
一般財団法人日本自動車研究所
ITS研究部
部長
谷川 浩
モデレーター

名古屋大学
未来社会創造機構/大学院情報学研究科
教授
高田 広章
セッション概要
P-1 パネルディスカッション「便利で快適なモビリティ社会の未来」
パネリスト
 鯉渕 健 氏
鯉渕 健 氏
1993年 トヨタ自動車に入社。車両運動性能開発等を経て、シャシー制御開発を担当。さらにパワートレイン系統合制御他幅広く制御システムの開発を経験。そして、2014年より自動運転技術、先進安全技術の開発を担当。現職は、トヨタ自動車 先進技術開発カンパニー 先進安全領域 領域長、及びトヨタ・リサーチ・インスティテュート・アドバンスト・デベロップメント株式会社 取締役 CTOを務める。
 清水 和夫 氏
清水 和夫 氏
武蔵工業大学電子通信工学卒
1981年からプロのレースドライバーに転向
1988年本格的なジャーナリスト活動開始
日本自動車ジャーナリスト協会会員(AJAJ)
日本科学技術ジャーナリスト会議 会員(JASTJ)
NHK出版「クルマ安全学」「水素燃料電池とはなにか」「ITSの思想」「ディーゼルは地球を救う」など
国家公安委員会速度取締り見なおし検討委員(終了)
NEXCO東道路懇談委員・継続中
国土交通省車両安全対策委員・継続中
内閣府SIP自動走行推進委員(2014~2019/6)
経済産業省・国土交通省 自動走行ビジネス検討会委員
経済産業省・国土交通省 自動走行の民事上の責任及び
社会受容性に関する研究検討会・継続中
 河野 文昭 氏
河野 文昭 氏
技術士(総合技術監理、情報工学)。前職のアイシン精機(株)入社から2003年までクルマの制御ブレーキ開発業務に従事。2004年から SW-CMM/CMMI を活用した開発プロセスの構築を牽引 (2012年 CMMI レベル4)。2009年よりクルマの制御ブレーキにおける機能安全開発業務に携わり、開発プロセス及び開発環境の整備、さらにはISO 26262に準拠した機能安全監査及びアセスメントに尽力中。
 谷川 浩
谷川 浩
1983年トヨタ自動車に入社、エンジン制御用電子システム,センサー開発、車内LAN・ソフトPFの国際標準化活動等に従事。自動車メーカー・サプライヤー連携テーマの企画、共同開発やビジネスの仕組みつくり、標準化活動などを幅広く経験し、2004年にはトヨタ自動車代表としてJaspar設立にも参画。
近年では先進的な制御システム開発や開発の仕組み作りなどに従事。2013年5月から日本自動車研究所に籍を置き自動走行関係事業の企画ならびに研究推進に取り組み、現在に至る。
モデレーター
 高田 広章 氏
高田 広章 氏
リアルタイムOSを中心に、組込みシステム設計・開発技術についての研究開発に従事。オープンソースのリアルタイムOS等を開発するTOPPERSプロジェクトを主宰。名古屋大学発ベンチャ企業APTJ(株)を設立し、その代表取締役会長・CTOを務める。博士(理学)。
B会場
サテライト会場(A会場の内容を中継して、プロジェクタで投影致します。)
時間
C会場
17:45~19:15(90分)
R-1 情報交換会 C会場
参加費:3,000円(税込)
※講演者やプログラム委員、出展社とともに有意義な交流を行えます。どうぞご参加下さい。
※参加費は当日懇親会会場にて領収証とお引き換えにお預かりいたします。
お支払いは現金のみとなりますので、釣銭のないようご準備をお願いいたしします。